https://youtu.be/u6DljfV0DxM
ちびまる子ちゃん「こどもの日の出来事」の巻(20:44)
5月5日は「こどもの日」ですね。端午の節句ともいいます! 子供の成長を願って、お祝いをする日ってことは、何となく分かるのですが・・・ はて(・・?「こどもの日」ってなんだろう?ってなりました。
小学校に通う「わが子」がいる今こそ、もう少し、この季節の行事について勉強してみたくなりました。 どうぞ、お付き合いの程、お願い致します。
端午の節句とは?
「端午の節句」=「こどもの日」は、奈良時代(710年~)から続いています。
端午というのは「月の端(はじめ)」の「午(うま)の日」という意味で、旧暦5月の、最初の丑の日とされていました。 語呂などにより、次第に「5月」の「5日」なったとのことです。
この季節の変わり目である「端午の日」に、「病気」や「災難」をさけるための行事が行われていた・・・名残が「こどもの日」になります。
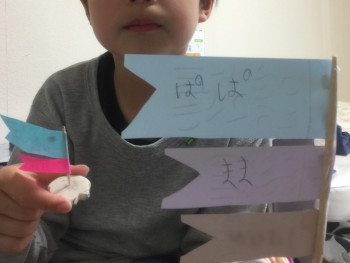 そして5月人形(武者人形や鎧兜)や鯉のぼりをあげるようになったのは、江戸時代(1603~)からです。
そして5月人形(武者人形や鎧兜)や鯉のぼりをあげるようになったのは、江戸時代(1603~)からです。
端午の節句は、徳川幕府にとって重要な日であり、大名や旗本が、江戸城に参って、将軍様にお祝いを奉じ、また将軍様に男の子が生まれると、馬印やのぼりを立てて喜びました。
これがやがて近代の「男の子のお祝い」となり、「病気」や「災難」を避け「成長を祝う」習慣として、一般に広まっていきました。
なぜ鎧兜(よろいかぶと)を飾るのか?
鎌倉時代(1185~)以降の武家社会では、甲冑は男性にとって身を守るための大切な道具でした。
 (※注:飾り方は中央に兜・向かって右側に太刀、左側に弓矢です)
(※注:飾り方は中央に兜・向かって右側に太刀、左側に弓矢です)
戦場で身を守ってくれる鎧兜は、子どもに災いがふりかからず、無事に成長するようにとの願いを込めて飾られています。
なぜ?鯉のぼりを立てるのか?
武士の家では、男の子が生まれると「のぼり」を立ててお祝いしました。漁師など、漁村では「大漁旗」を使ってお祝いするところもあるようです。

庶民は、のぼりを立てられなかったので、かわりに「鯉のぼり」を・・・「鯉が竜門の滝を登ると竜となって天をかける」という中国の伝説より、立身出世を願って立てられていったとも言われています。
 鯉のぼりとして、魚を青空に泳がせるという発想は、日本人独特の感性です。
鯉のぼりとして、魚を青空に泳がせるという発想は、日本人独特の感性です。
他にも○○があるよ!
ゴールデンウィーク期間中の「こどもの日」ですので、家族で楽しめる〇〇の3つを紹介します。
菖蒲湯(しょうぶゆ)に入ろう!
急に暑くなるこの時期は、昔から、病気に掛かったり、体調を崩したりする人が多くなります。
端午の節句では、薬草摘みをして配ったり、薬草風呂や薬草酒を飲んだりという習慣もあったようです。 芳香があり匂いが強く、葉っぱや根っこは、漢方薬などの胃薬、解熱、ひきつけ、創傷などの薬になっています。
また、菖蒲は夏の病を防ぐ呪力があるという信仰で、家の軒に挿して「おまじない」をしたり、菖蒲の鉢巻をしたり、腰に挿したり、兜に付けて「石合戦」をして遊んだりもしたようです。
菖蒲湯は、葉っぱや根っこを湯の中に浮かべることで、リラックスし、ストレス低減し、血行促進、腰痛などに効果があります。
「ちまき」を食べよう!
こどもの日に「ちまき」を食べる由来は、諸説あるようです。
有力なのは、楚の王様の側近であった屈原(くつげん)という人物が、5月5日に川に身を投げて、民衆は死んだことを憐れんで、葉で餅を包んだものを五色の糸(竜の嫌う色)で縛って供えていたというような、中国の古事より伝わったものらしいです。

柏餅を食べよう!
「柏餅(かしわもち)」は、日本独自のものです。
柏の葉っぱは、他の新しい芽が生えてくるまで、古い葉が落ちないことから、家系が絶えないよう子孫繁栄を願って、子供の無事を願って食べる縁起担ぎになります。

関東地方では「柏餅」、関西地方は「ちまき」が多く食べられているようです。
女の子は「おまけ」なの?
江戸時代あたりから、男の子のための行事というイメージが大きくなってきたのではないでしょうか?

でも、古くは男女関係なく、子供の成長を祈願する日として、親しまれていましたので、遠慮なく、みんなでお祝いをしましょう。

まとめ
こどもの日について、理解を深めることができて良かったです。ちなみに、ゴールデンウィーク期間中ですので、有名な鯉のぼり群を見に行ったり、端午の節句にちなんだ食べ物を食べたり、菖蒲湯に入ったり、お祝いして、家族で楽しみたいと思っています。
子供の成長は、願ってもないことですので、楽しいことを存分にやってあげたいです!
















